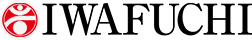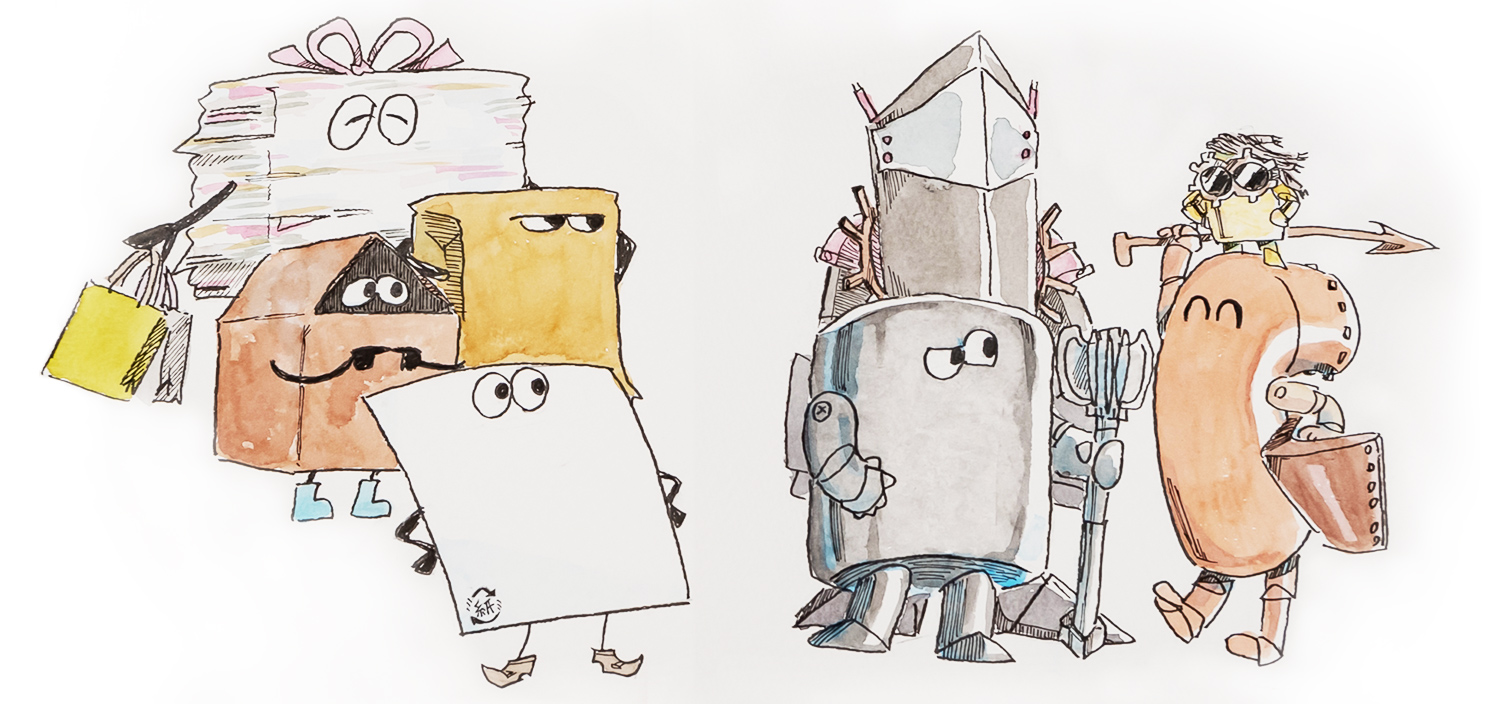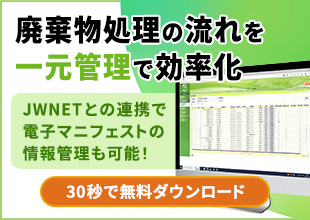プラスチックはそのまま処分する前に、きれいに洗った方が良いと聞いたこともあるのではないでしょうか?
プラスチックは今、再利用できる重要な資源として、さまざまな物にリサイクルされています。
だからこそ、プラスチック製品を処分する前に、どのような処分方法が環境に優しいのか把握しておきましょう。本記事ではプラスチックは洗って捨てるべきか、分別は必要かなどをくわしく紹介します。
また、正しい処分方法も解説するためぜひ参考にしてください。
目次
プラスチックごみの正しい処分がリサイクルにつながる

プラスチックごみを資源として再利用するには、「きちんと洗ってから分別する」ことが基本です。
なぜなら汚れが付着したままでは再利用が困難になり、燃えるごみに回されてしまうのです。
自治体ごとに分別ルールは異なるものの、多くの場合「プラマーク」があるものは「プラスチックごみ」として処理されます。正しい分別と処理こそ、プラスチックを無駄にせず資源循環にするための第一歩です。
特に食品トレーや飲料用のペットボトルなどは軽く水洗いして、汚れを落とすだけでもリサイクル率の向上につながるため、一人ひとりの行動を見直しましょう。
知っておきたい「プラスチックごみ」の種類

一口にプラスチックごみといってもその種類はさまざまで、リサイクルのためには、用途や形状に応じた適切な分別が求められます。
たとえば、食品の包装やカップ麺の容器など、プラマークが付いた家庭ごみは「容器包装プラスチック」として回収される方法が一般的です。
また、ペットボトルやレジ袋もそれぞれ別の扱いとなるケースが多いため、自治体のガイドラインを確認しましょう。
ここではプラスチックごみの大まかな種類別の特徴と、どのように分類されるか解説します。
食品包装材・容器
弁当のふたやカップ麺の容器、調味料のパックなど、食品に関連するプラスチック容器は「容器包装プラスチック」に分別される自治体が多くあります。
リサイクルのためには中身を使い切り、軽く洗ってから出しましょう。油汚れなどが残っているとリサイクル工程に支障をきたすため、家庭での洗浄が必要です。
しかし汚れがひどく落ちにくい場合は、無理せず「燃えるごみ」として処理することも一つの方法です。
ペットボトル
ペットボトルは、リサイクルが進んでいる代表的なプラスチックごみです。
回収時には「キャップ」「ラベル」「本体」の3つに分けて処理しましょう。
キャップとラベルは「プラスチックごみ」として、本体は「ペットボトル専用回収」に出してください。また、ボトル内に飲み残しがないようにし、軽くすすいでから潰して出すことも心がけましょう。潰すことでゴミ袋におさまる量が増え、回収・運搬の効率も上がります。
面倒ですがいつも飲んでいるペットボトルは、飲み終わったらすぐにラベルとキャップをはがし、軽く洗い流す習慣を意識してみましょう。
レジ袋
レジ袋は自治体によって分別のルールが異なりますが、基本的にはプラスチックごみに分類されます。ただし、レジ袋が汚れている状態ではリサイクルできないため、きれいな状態のものだけをプラスチックごみに分類しましょう。
また、匂いや異物の付着もリサイクルできない原因のため、汚れが気になる時は事前に水洗いしたうえで干して乾燥させる方法がおすすめです。
なおレジ袋は一枚ずつ分けた状態でプラスチックごみに出すと、さらに丁寧です。
二重や三重に重なった状態のレジ袋は、一枚ずつの分別に手間がかかるため。リサイクル作業をスムーズに進めるためにも口を結ばずに一枚ずつの状態でプラスチックごみに出してください。
プラスチック製スプーンやストロー
コンビニやカフェなどで提供されるプラスチック製のスプーンやストローは、「燃えるごみ」として扱われる自治体が多くあります。
また、再利用可能な場合はプラスチックごみに該当するケースもあります。しかし、あくまでも容器包装プラスチックではなく、製品の扱いになる点が大きな違いです。リサイクルが難しいアイテムの一つであり、軽量でコンパクトだからこそポイ捨てにより海洋ごみにつながるリスクも問題視されています。
そのため、プラスチック製のカトラリーを受け取らず、持ち歩くなどして使用頻度を減らす方法も検討しましょう。
釣り糸
釣り糸はナイロンなどのプラスチック素材で作られていますが、主に燃えるごみに分類されます。
長さが30cmを超える場合は、粗大ごみに分類される場合もあるため自治体の情報をチェックしましょう。
なお、釣り針は不燃ごみや危険物の扱いが多いため、必ず分別したうえでそれぞれ正しく処分してください。
釣り糸は海や川に放置されると重大な環境問題を引き起こします。水中に長期間残り、魚や鳥、ウミガメなどが絡まって命を落とすこともあるため、ポイ捨てしないよう取り扱いに十分注意してください。
プラスチックごみの分別・処理の流れ

プラスチックは分類が多いですが、分別した方がリサイクル効率をあげる結果につながります。
大きく分けて容器包装プラスチック、製品プラスチックがあります。
「容器包装プラスチック(プラマーク付き)」は、自治体によって回収・再資源化されるため、洗って乾かしたうえで分別して自治体の指示通りに処分しましょう。
ただし、すべての自治体がプラスチック分別を導入しているわけではなく、一部地域では焼却処分が前提のところもあります。
プラスチックの中でも、可燃、不燃、資源化されるものの違いを見ていきましょう。
可燃ごみ
・汚れがひどく洗浄が難しい食品トレイ
・プラマークのないビニール
・破損したプラスチック製品(おもちゃ・ハンガーなど)
これらは再利用が難しいため、可燃ごみとして処理するよう指定されている自治体が多くあります。
また、容器包装プラスチックであっても、汚れが付着したままだとリサイクル工程に適さないケースもめずらしくありません。きれいに洗って乾かすことが難しい場合は、無理に分別せず可燃ごみに出す方が、逆に処理がスムーズになります。
不燃ごみ
・金属やガラスなど別素材と一体になった製品
・硬質で大型(洗面器・バケツなど)
プラスチック以外の素材や、大型の製品は可燃ごみとして処理できず不燃ごみの扱いになる自治体があります。
これらは燃やしてもエネルギー回収効率が低く、処理にコストがかかるため、通常の焼却施設では扱いづらいことが現状です。自治体の分別ルールをよく確認し、適切なごみ袋や指定日に出すよう心がけましょう。
資源化
プラスチックごみの中で、再利用可能なものは「資源化」の対象です。
中でもプラマークのついた容器包装プラスチックは、自治体が分別回収し、洗浄・溶解などの工程を経て再び製品原料として生まれ変わります。
また、ペットボトルも専用のリサイクルルートが確立されており、繊維や新たな容器に再加工されるのです。ただし、資源化には「正しい分別」と「ある程度の清潔さ」が必要です。だからこそリサイクルを無駄にしないためにも、家庭で洗浄するひと手間が重要です。
産業系廃プラスチックはリサイクルされやすい

産業分野から排出される廃プラスチックは、一般家庭のプラスチックごみと比べてリサイクルされやすい傾向にあります。
その理由の一つは、汚れの少ない点です。たとえば、製造業や物流業から出るプラスチックは比較的均一な素材で汚染が少なく、回収・再処理の手間が少ないため高い割合で資源化が可能です。
一方、家庭から出る食品トレーや容器包装は、食品残渣が付着しやすく汚れたままでは再利用が困難という違いがあります。
ただし、家庭ごみでも使用後にさっと洗って汚れを落とすだけで、リサイクル可能な割合はぐんと上がります。
産業系と同様に“きれいな状態”で排出する意識を持つことが、資源循環社会への一歩です。
プラスチックは洗うべき?理由と注意点

プラスチックごみをリサイクルに回すには、食品の容器などは汚れが付着したままだと、工程で悪臭や衛生面の問題が生じてしまいます。
また、他のリサイクル可能なプラスチックも一緒に廃棄される恐れがあるため適度に家庭での洗浄が必要です。
以下に、洗浄のコツと注意点をご紹介します。
軽くすすぐだけで十分なケースもある
プラスチックごみは、必ずしも洗剤を使ってピカピカにする必要はありません。
ヨーグルトの容器やお惣菜パックなど、汚れが落ちやすいものは水で軽くすすぎましょう。ゴミ出しのついでに水道の残り湯を使ったり、他の食器を洗うついでにさっと流すだけでも、リサイクルに回せる状態になります。
重要なのは、悪臭やカビの原因になるような汚れを残さないことです。無理なく取り組める範囲での洗浄を習慣づけることが、持続可能なリサイクルにつながります。
お湯を使うことはNG
プラスチック容器を洗う際に、お湯を使ってきれいに汚れを落とそうとするのは。変形や有害物質が溶け出すリスクがあります。
また、溶けたプラスチックが排水管内で固まり、パイプ詰まりの原因です。すすぎは常温の水で、汚れがひどい場合でもぬるま湯程度にとどめるのが安心です。安全かつ効果的な洗浄を心がけましょう。
水の使いすぎも環境負荷につながる
プラスチックごみをリサイクルに回すには、汚れを落とすための“洗浄”が欠かせませんが、ここで注意したいのが「水の使いすぎ」です。
環境への配慮という観点では、リサイクルのために大量の水を使用するのは本末転倒。洗剤やお湯を多用すると、排水処理の負担やエネルギー消費が増え、かえって環境への影響が大きくなる恐れがあります。そこで食器洗いのついでにさっと流したり、水の再利用で汚れを軽く落とすよう心がけましょう。
この普段の皿洗いでの「ついで洗い」による、意識が持続可能な社会づくりにつながるのです。
まとめ
プラスチックは再利用できる製品が多い一方、汚れや悪臭があるとリサイクルできないデメリットがあります。
だからこそ、家庭での汚れを落とすための軽い洗浄や、正しい分別がリサイクル率向上に欠かせません。
プラスチックは石油由来で作られているからこそ、限りある資源を守り循環化を促すためには、家庭一人ひとりの心がけが重要なのです・
これまで何気なく燃えるごみなどに捨てていたプラスチック製品も、リサイクルできる可能性があるため、この機会にぜひ処分方法を見直してみてはいかがでしょうか。