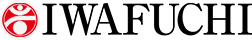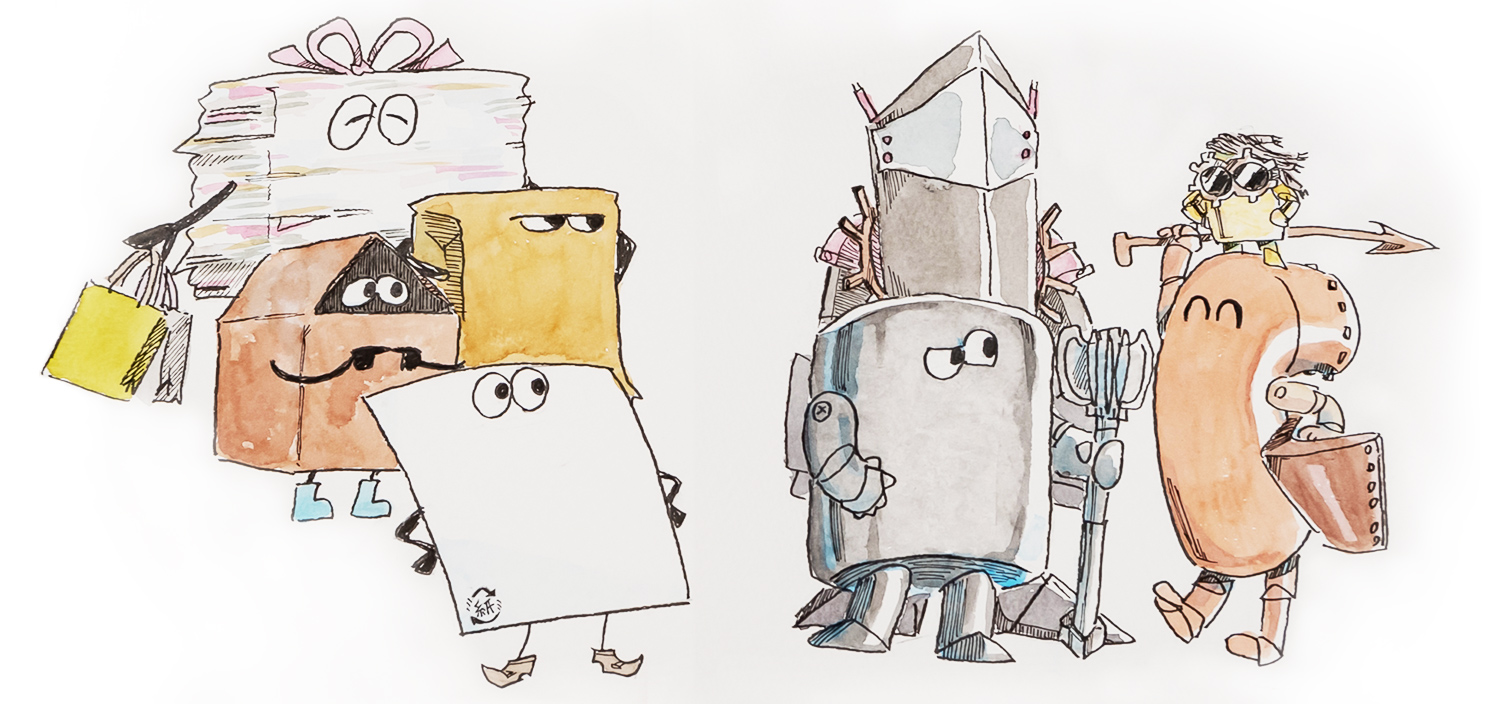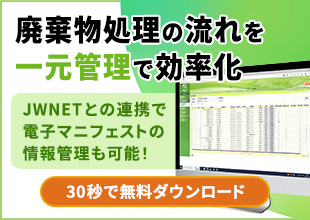資源物は不用品を回収後に、リサイクルできる物の呼び名です。再利用することで資源を守るだけでなく、地域の集団資源回収は地域活動の資金にも役立てられています。
本記事では資源物とは何か、区分別での特徴を紹介します。また資源物の正しい処分方法も解説するため、ぜひ参考にしてください。
目次
資源物とは?

資源物とは「再資源化(リサイクル)」できる廃棄物の総称です。リサイクルできる資源といえば、主に空き缶やペットボトル、故紙を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
他にも金属、布などいろいろな素材が再資源化によって、生活に欠かせないアイテムとして活用されています。
資源物は素材や種類ごとに細かく区分されており、処分方法も自治体によって異なります。
せっかくの資源物も間違った処分方法を選べば、再利用されずごみになってしまいます。少しでも今ある資源を有効活用するためにも、正しく資源物を区分別で分けてリサイクルに出しましょう。
資源物の区分

資源物の区分、再利用される製品の例を紹介します。
| 区分 | 再利用(再製品化)の例 |
|---|---|
| 紙類(段ボール) | 段ボール・故紙・紙筒 |
| 紙類(雑誌) | 段ボール・ボール紙箱・絵本・新聞紙・印刷用紙など |
| 紙類(新聞) | 絵本・新聞紙・週刊誌・印刷用紙など |
| 紙類(コピー用紙・牛乳パック) | トイレットペーパー・ティッシュペーパーなど |
| 布類(中古衣料) | 海外に輸出 |
| 布類(古布) | 工業用ウエス(雑巾) |
| ビン・カン類(ガラス瓶) | ガラス瓶・断熱材・アスファルト舗装・カラー舗装など |
| ビン・カン類(スチール) | スチール缶・自動車・家電などの資源 |
| ビン・カン類(アルミ) | アルミ缶・アルミサッシ・自動車部品など |
| ペットボトル | 食品容器(卵パックなど)、カーペット、洗剤用・飲料用ボトル、結束バンド、ごみ袋など |
| プラスチック製容器 | 食品容器、断熱材、文具、ごみ袋など |
| スプレー缶・ガスボンベ | 自動車部品、鉄骨、レールなど |
| 廃食油 | タイヤ・ゴムの軟化剤、石鹸・洗剤の脂肪酸原料など |
| 使用済み小型家電 | 鉄・アルミニウム・プラスチックに分けて原料を再利用 |
資源物になるか判断に悩む物があれば、自治体が発行している「ごみの手引き」や公式ホームページに記載されている情報をチェックしましょう。
資源物にならない種類

- 汚れた紙:ピザの箱、ティッシュ、油染みのある紙など
- 紙コップ(紙皿:防水加工のため)
- シュレッダーごみ(飛散防止のため一般ごみ扱い)
- 濡れた布・破れた布団やカーペット類
- 割れたガラスや陶器
- 化粧品や薬品の空き容器
- スプレー缶に中身が残っているもの(危険物扱い)
- 汚れが落ちないプラスチック容器
- 食品が付着した発泡スチロールやトレー類
- 乾電池(有害ごみや別回収扱い)
- 電球・蛍光灯(専用回収)
- ライターや使い捨てカイロ(発火・発熱の危険)
上記の「資源物にならないもの」を資源ごみに混ぜてしまうと、リサイクル工程が止まるなどのトラブルの原因です。
場合によっては、処理中に引火や爆発を起こし、大きな火災の原因になる可能性もあります。
必ず分別ルールを守り、安心・安全なごみ出しを心がけましょう。
資源物の正しい処分方法

資源物別での処分方法を紹介します。何気なく捨てていた資源物も、処分方法を見直すとリサイクル率アップに役立ちます。
紙類
- 新聞紙
- 雑誌
- 段ボール
- 紙パックなど
紙類は上記のような紙を使った製品が該当します。ただし汚れた紙や防水加工された紙はリサイクルできない場合が多いため注意しましょう。
ノートやプリントなど、鉛筆、ボールペンで書き込んだ程度の紙類は、そのまま資源ごみとして出せます。
そのため、他の故紙とは一緒にせず燃えるごみなど自治体の指示に従って処分してください。基本的に紙類は種類ごとにまとめて、ひもでしばって出す方法が一般的です。
牛乳などの紙パック、段ボールなどは、それぞれ分けて資源ごみとして回収する場合もあります。
布類
- 衣類
- タオル
- シーツなど
濡れたり汚れたりしている布類は、リサイクルできないことがあります。汚れが気になる際は、処分前に布類は洗濯して乾かしましょう。
布団などの大型の布類は、ひもで縛るか大きな透明の袋に入れて出すことが推奨されています。
自治体によっては無料回収日や回収場所が定められているケースもあるため、確認しておきましょう。
ビン・カン類
- 飲料用
- 食品用のビン・カン
飲料や食品のビン・カンは中身を使い切り、水洗いしてから処分しましょう。
ただし、ビンやカンのフタは本体と分別が異なる場合があります。素材が違うのであれば、自治体の指示に従って分けておきましょう。
なおカンの中でもペンキなど汚れが付着している場合は、埋め立てごみや燃えないごみなどに分類されます。
ペットボトル
- 飲料用のペットボトル
- 調味料のボトル
ペットボトルはプラスチック製品のため、資源物として再利用されています。キャップとラベルを外し、中をすすいできれいにした状態にしましょう。
また、ごみ袋に多く収まるように、可能であれば潰して出すことが推奨されています。
なおペットボトル本体部分と、キャップやラベルは分別方法が異なります。
キャップやラベルは主にプラスチック製容器包装として扱われるため、自治体の分別方法をチェックしましょう。
プラスチック製容器
- 食品トレー
- 洗剤のボトルなど
プラスチック製の容器包装は、発泡スチロールとも呼ばれており資源物に該当します。中身を使い切り、汚れを落としてから処分しましょう。
洗っても落ちない汚れや、汚れの範囲が広い場合は、燃えるごみとして処分する場合もあります。
スプレー缶・ガスボンベ
- ヘアスプレー
- 塗料用スプレー
- ガスボンベなど
スプレー系は中身を完全に使い切り、穴を開けてから出すのが一般的です。ガスが残っていると火災の原因になるため、取り扱いには十分注意しましょう。
自治体によっては、穴を開けずに資源物に出すことを指示している場合もあります。
事故を防ぐためにも不明な点は調べたうえで、正しい方法で分別しましょう。
廃食油
使用済みの食用油が対象です。油の固形剤を使って固めるか、新聞紙などに染み込ませて燃えるごみとして出しましょう。自治体によっては、廃食油専用の回収容器を設置している場合もあります。
使用済み小型家電
- 携帯電話
- デジタルカメラ
- 電気ケトルなど
小型家電はごみ袋に入る程度の大きさの家電が主に該当します。自治体の指定する回収ボックスに出すか、指定の方法で処分することが求められます。
特にスマートフォンなど個人情報が含まれる機器は、データの消去を忘れずに行いましょう。
資源物を処分するときの注意点

収集日・回収方法は自治体ごとに異なる
資源物の分別や収集方法は全国で統一されておらず、自治体ごとに細かなルールがあります。
たとえば、東京23区ではビン・カン・ペットボトルが一括回収される地域もありますが、他の自治体では週ごとに回収品目が変わるケースもあります。
紙類では「雑誌・新聞・段ボール・紙パック」の分類を求められる地域もあり、混在すると収集できないなど、ルールはさまざまです。
また、使用済み小型家電やスプレー缶などは通常のごみと一緒に出せず、スーパーや家電量販店に設置された専用ボックスへの持ち込みが必要な自治体もあるため、事前に調べておきましょう。
こうした違いを知らないとリサイクル工程の妨げになることもあるため、自治体が発行している「ごみ分別ガイド」やアプリを活用してください。
汚れたもの・異物混入はリサイクルの妨げに
リサイクルの現場では、汚れた資源物や異物が混ざると再利用が難しくなったり、処理そのものがストップすることがあります。
たとえばペットボトルの中の飲み残し、プラスチック容器にソースや油が付着している状態では、洗浄や分別に余計な手間がかかる原因です。
他のきれいな資源物まで、処理対象外となってしまうリスクもあります。
また、紙類の中でも紙コップや紙皿のような防水加工された製品は、リサイクルに不向きとされています。
見た目が紙でも、分別区分としては「燃えるごみ」に該当する場合が多いため注意しましょう。
リサイクルに出す際は「きれいに洗って乾かす」ことが基本ルールです。
きれいな状態で資源ごみとして出せば、リサイクル率の向上に役立ちます。
安全のため中身の確認と処理を忘れずに
処理の仕方によっては、危険を伴う資源物があります。特にスプレー缶やカセットガスボンベなどの圧力容器は、火災のリスクがあります。
中身が残っていたり、穴を開けた状態で可燃物と一緒に出すと、収集車の火災や爆発につながるため、使い切りましょう。
自治体によっては「必ず穴を開ける」「逆に穴を開けずに出す」など対応が異なります。そのため、処分前に捨て方の確認が必要です。
また、使用済みの小型家電の爆発事故も増加しています。スマートフォンやデジカメにはリチウムイオンバッテリーが内蔵されており、落下などで損傷すると発火の恐れがあります。
出す前にバッテリーの有無を確認し、可能な限り取り外したうえで家電量販店などに設置された専用回収ボックスに出しましょう。
まとめ
資源物は正しくリサイクルすると、再製品化できる種類がたくさんあります。
しかし、処分方法を間違うと、爆発や火災などのリスクもあるため、自治体の指示に従って処分しましょう。
まずはごみとして出す前に、資源物になるか確認してみることを心掛けてみてください。