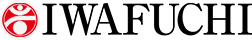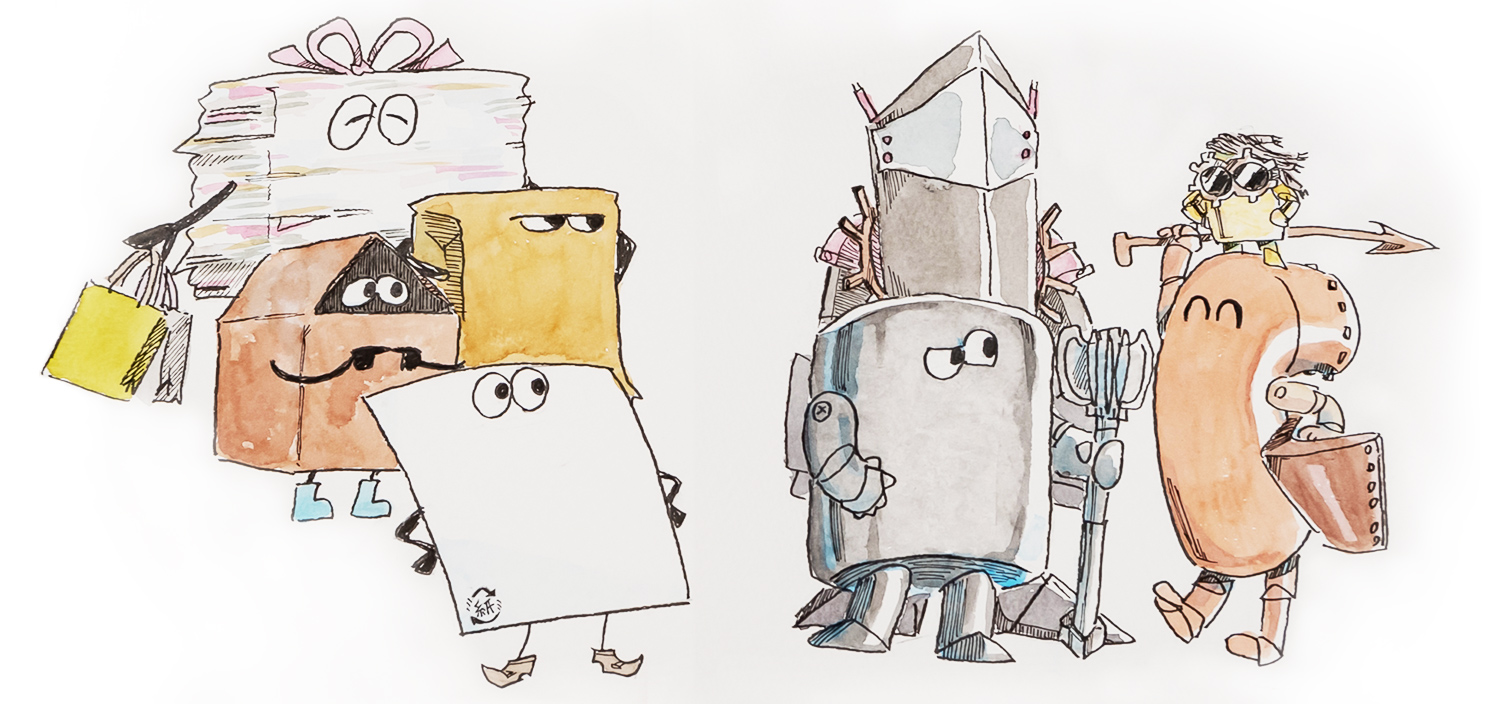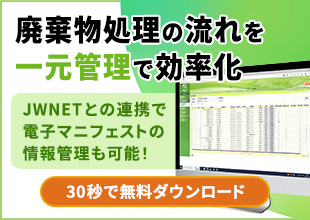バイオマスプラスチックは、プラスチックごみの環境汚染を解決するために考えられた新しい素材です。
本記事ではバイオマスプラスチックの原材料や作り方など、気になるポイントを解説します。
バイオマスプラスチックを使うメリットや、現在の課題を知り、これからの商品選びやリサイクル方法の見直しの参考にしてください。
バイオマスプラスチックとは?

バイオマスプラスチックは、植物などの再生できる資源で作られたプラスチックです。
サトウキビ、とうもろこしが主な原料で、部分的にバイオマスプラスチックを使ったプラスチック製品もあれば、全面的にバイオマス原料で作られた製品も存在します。
バイオマスプラスチックは、石油資源を使わずに再生可能な植物由来の原料で作られているため、環境に優しく限りある資源の節約につながるため世界的に注目されています。
バイオプラスチックとの違い
バイオマスプラスチックとバイオプラスチックは、次のような違いがあります。
- バイオマスプラスチック:再生可能な有機資源が原料
- バイオプラスチック:バイオマスプラスチックと生分解性プラスチックの総称
バイオプラスチックは、微生物の働きによって水と二酸化炭素まで分解される「生分解性プラスチック」と、バイオマスプラスチックの総称です。
どちらも最終的に自然に分解される特性があり、従来の化石原料のプラスチックとは違う新しい素材です。
バイオマスプラスチックの作り方
バイオマスプラスチックは、発酵法と化学合成法の2つがあります。
どちらも再生可能な原料を使っている点は共通ですが、次のように製造過程が異なります。
- 発酵法:植物原料を発酵させてエタノールなどの中間原料を作り樹脂を生み出す
- 化学合成法:糖分や油脂を化学合成して樹脂を生み出す
でんぷんを酵素分解して作った糖を、さらに乳酸菌発酵させてポリ乳酸を作り出します。このポリ乳酸を加工すると、プラスチック製品ができあがります。
バイオマスプラスチックは2種類ある

バイオマスプラスチックは、生分解性だけでなく非生分解性の種類も存在します。
それぞれのバイオマスプラスチックの特徴と違いを見ていきましょう。
生分解性バイオマスプラスチック
生分解性バイオマスプラスチックは、プラスチック製品の廃棄処理でバクテリアや菌の力によって水と二酸化炭素まで分解できる種類です。
生き物の力によって、最終的に無害な水と二酸化炭素まで分解されるため、プラスチックごみの放置や焼却処分時に発生する有害物質の削減につながります。
非生分解性バイオマスプラスチック
非生分解性バイオマスプラスチックは、微生物や菌で分解されませんが、燃やしてもCO2などの有害物質の排出を抑制できます。
廃棄時にCO2濃度の上昇を抑えられるため、地球温暖化抑止などの効果が期待されます。
バイオマスプラスチックの活用方法

バイオマスプラスチックは、植物由来の原料を使用した環境に優しい素材として注目されています。従来の石油由来に比べ、二酸化炭素の排出削減や資源の持続可能性といったメリットがあり、私たちの生活のさまざまな場面で活用されています。
ここではバイオマスプラスチックが実際にどのような製品になっているのか、具体的な活用例を紹介します。
レジ袋や使い捨て包装用容器
バイオマスプラスチックの身近な使用例は、レジ袋や使い捨ての食品容器があります。日本ではプラスチックごみ削減のためにレジ袋の有料化が進んでいます。
このレジ袋こそがバイオマスプラスチック製で、多くの店舗で採用されているのです。コンビニやスーパーだけでなく、テイクアウト用のカップやカトラリーなどにも広く利用され、環境負荷の少ない選択肢として普及が進んでいます。
農業
バイオマスプラスチックは、農業分野でもさまざまな形で活用されています。特に、農業用フィルムやマルチシート、ポットなどで利用されることが増えています。
生分解性のあるバイオマスプラスチックを使用すれば、廃棄の手間が省けて処理コストの削減が期待できます。
従来の農業用プラスチックは大量使用により、廃棄が課題でしたが、バイオマスプラスチックの導入で持続可能な農業が実現しつつあります。
医療
医療分野でも、安全性や生分解性を活かしたバイオマスプラスチック製品が増えています。
たとえば手術用の吸収性縫合糸や人工関節などで活用されています。ほかにも、点滴バッグや手袋など使い捨ての医療器具にも、バイオマスプラスチックが役立っているのです。
特に手術で使われる生分解性の縫合糸は体内で自然分解されるため、抜糸の必要がなく、患者の負担軽減にもつながっています。
自転車
自転車のフレームや部品にも、バイオマスプラスチックが活用されています。従来の金属製やカーボン製のフレームに比べ、軽量かつ環境負荷の少ない素材です。
特に環境に配慮したエコな自転車の需要が高まっており、これからもバイオマスプラスチックを活用した製品がさらに増えていくと考えられます。
衣料の繊維
衣類にもバイオマスプラスチックを使った製品が、サステナブルファッションの一環として注目されています。
たとえば、トウモロコシ由来のポリエステル繊維などが開発されており、従来の石油由来の合成繊維と比べて環境負荷の軽減になります。
また、速乾性・耐久性を兼ね備えた高性能なバイオ繊維も増えています。特にスポーツウェアやアウトドア用品の分野では、高機能で環境に優しい素材が求められており、バイオマスプラスチック繊維が注目されています。
電気機器
バイオマスプラスチックは、家電製品や電子機器の部品にも使われています。テレビやパソコンの外装をはじめ、電気絶縁性や耐久性に優れたバイオプラスチックの開発が各メーカーで進められているのです。
また、家電や電子機器のスムーズなリサイクルで、循環型社会にも貢献できます。このように私たちの身近な製品にも多く採用され、環境に配慮した選択でさらにエコな暮らしの実現につながります。
バイオプラスチックを使うメリット

バイオプラスチックは、植物由来の原料を使用した環境に優しいプラスチックとして注目されています。
ここでは、バイオプラスチックを使用する主なメリットを解説します。
二酸化炭素の排出量を削減する
バイオプラスチックのメリットの一つが、二酸化炭素の排出削減です。従来のプラスチックは原油を使用し、製造過程や焼却処分の際に大量の二酸化炭素を排出します。
一方で、バイオプラスチックはトウモロコシやサトウキビなどの植物原料で、植物が成長する過程で二酸化炭素を吸収するため、環境への負荷の軽減が可能です。
バイオプラスチックの活用は二酸化炭素の排出量が抑えられるだけでなく、カーボンニュートラルの実現にも貢献できます。特に企業や自治体の脱炭素社会を目指す動きが加速している中で、バイオプラスチックの導入は持続可能な社会の実現に向けた重要な選択肢なのです。
原油への依存度を下げられる
バイオプラスチックは、原油依存の軽減に貢献できます。プラスチック製品の多くが石油を原料としていますが、原油は限りある資源です。
価格変動の影響を受けやすい問題もあり、石油に依存しない製造方法が求められています。
バイオプラスチックは、サトウキビやトウモロコシ、ジャガイモなどの植物を原料とするため、再生可能な資源を活用できる点が大きな強みです。これまでは食品として流通されず、廃棄コースだった植物を副産物として資源活用できれば環境負荷の低減にも貢献できるでしょう。
海洋プラスチックごみ問題の解消に役立つ
バイオプラスチックは、海洋プラスチックごみ問題の解決にも貢献できます。近年、海洋に流出するプラスチックごみの増加が、深刻な環境問題になっています。
海洋ごみは海洋生物への悪影響や生態系の破壊リスクがあり、従来のプラスチックは自然界で分解されにくいデメリットがあります。
一度海に流れ出すと長期間にわたって環境に残り続けることが、プラスチックごみの課題でした。
バイオプラスチックの中には、生分解性を持つものもあり、適切な条件下で自然に分解される特性を持っています。ただし、生分解性のバイオプラスチックでも全てが自然界で短期間に分解されるわけではないため、適切な廃棄やリサイクルの仕組みを整えることが重要です。
バイオマスプラスチックの課題

バイオマスプラスチックは、環境に優しい素材として注目される一方、普及を進めるためにはいくつかの課題を解決する必要があります。
ここでは、バイオマスプラスチックが抱える代表的な課題について解説します。
製造コストがかかる
バイオマスプラスチックの最大の課題の一つが、製造コストの高さです。従来の石油由来のプラスチックと比べて、バイオマスプラスチックの生産にはより多くの費用がかかります。その主な理由が原料のコストの高さです。
バイオマスプラスチックは、トウモロコシやサトウキビなどの植物を原料としているため、農作物の生産状況や市場価格の影響を受けやすいです。
気候変動や農業政策による影響で原料価格が変動し、安定した供給がまだ難しい状況なのです。
また、植物から抽出した成分を化学的に加工する必要があり、その製造プロセスは石油由来のプラスチックよりも複雑です。全国的に設備が整っていないため、引き続き設備投資や研究開発費がかさむ現状と言えます。
耐久性がやや低い
バイオマスプラスチックは、従来の石油由来のプラスチックに比べて耐久性が劣る場合があります。生分解性を持つバイオマスプラスチックは、使用環境しだいで強度や耐熱性に問題が生じることがあります。
たとえば湿気や温度変化の影響を受けやすく、長期間の使用には向いていません。特に、生分解性プラスチックは、自然環境での分解を前提に設計されているため、長期間の保存や過酷な環境下では劣化が早まることがあります。
また耐熱性が低く、高温下で変形しやすいものもあります。例えば、食品容器や電子機器の部品に使用する場合、バイオマスプラスチックを使用できない可能性もあるのです。
まとめ
バイオプラスチックは従来のプラスチックとは違い、自然環境で分解される植物由来の原料で作られています。
バイオマスプラスチックは、環境負荷の低減に貢献できる一方で、いくつかの課題も抱えています。特に、製造コストの高さと耐久性の課題が、普及を妨げる要因となっています。
今後、技術の進歩や政策の支援で課題が克服されれば、ますますのバイオマスプラスチックの普及が期待されます。
環境に優しい選択肢として企業や消費者が積極的にバイオマスプラスチックを活用し、持続可能な社会の実現に貢献しましょう。