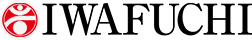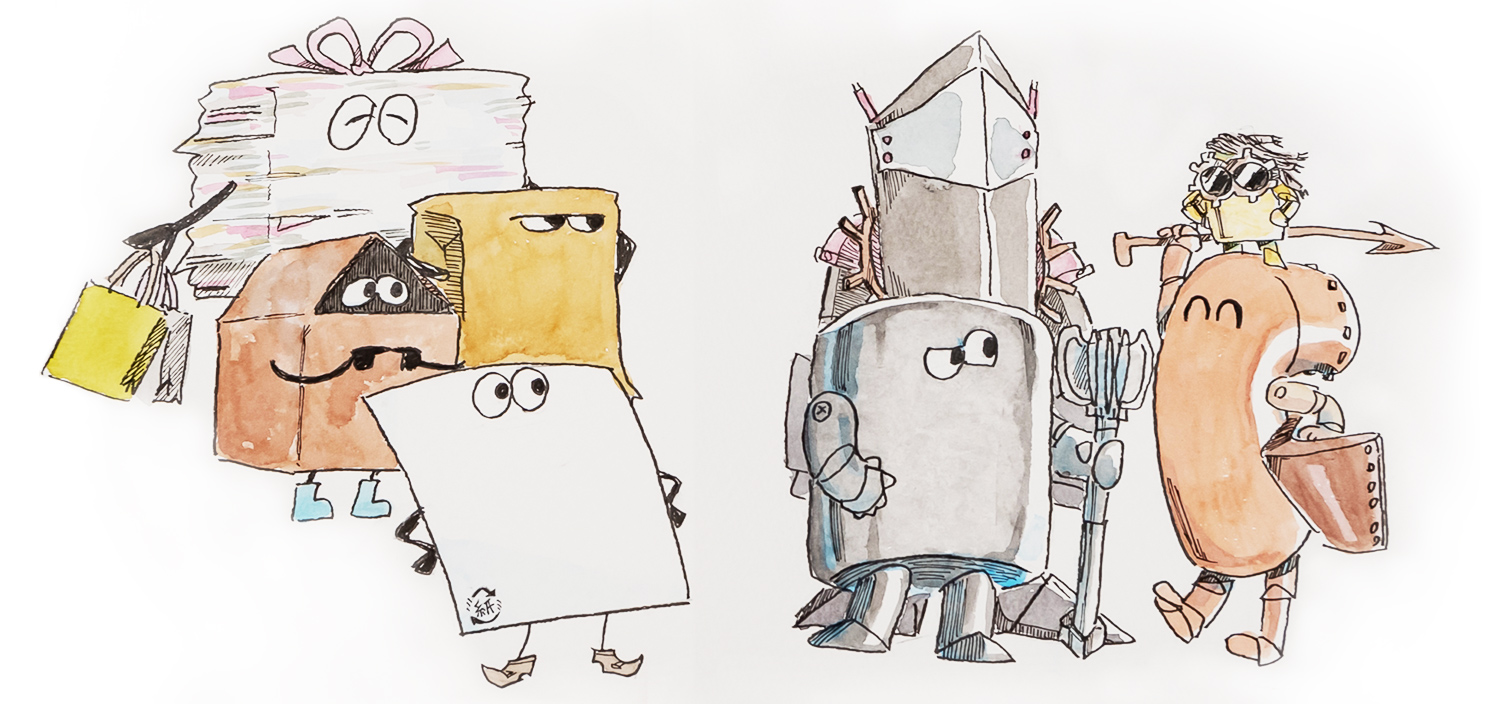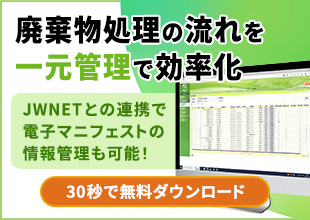「SDGs(エス・ディー・ジーズ)」とは、日本語で「持続可能な開発目標」の意味をもち、世界共通で定められた目標のことです。
SDGsに関する取り組みを実施している企業も多いですが、「SDGsに関して日常生活でできることはあるのか?」と疑問をもつ方も多いと思います。
リサイクルやフードロスの削減など、日常生活でできるSDGsの取り組みは多くあり、一人ひとりが取り組むことで目標達成に近づきます。
本記事では、SDGsの概要や日常生活でできるSDGsの取り組みを紹介します。
目次
SDGsの概要

SDGsは「Sustainable Development Goals」の略称で、気候変動や貧困など世界中で起きている問題を解決するため、世界共通で定められた目標です。
2015年に開催された国連サミットで採択され、2015年から2030年までの長期的な目標として、17の目標と169のターゲットで構成されている点が特徴です。
SDGsは世界で取り組み、「誰一人取り残さない」(leave no one behind)ことを理念にしており、日本でもさまざまな形で目標達成を目指しています。
SDGsの17の目標
SDGsの17の目標は、以下のとおりです。
| 目標1 | 貧困をなくそう |
|---|---|
| 目標2 | 飢餓をゼロに |
| 目標3 | すべての人に健康と福祉を |
| 目標4 | 質の高い教育をみんなに |
| 目標5 | ジェンダー平等を実現しよう |
| 目標6 | 安全な水とトイレを世界中に |
| 目標7 | エネルギーをみんなにそしてクリーンに |
| 目標8 | 働きがいも経済成長も |
| 目標9 | 産業と技術革新の基盤をつくろう |
| 目標10 | 人や国の不平等をなくそう |
| 目標11 | 住み続けられる街づくりを |
| 目標12 | つくる責任つかう責任 |
| 目標13 | 気候変動に具体的な対策を |
| 目標14 | 海の豊かさを守ろう |
| 目標15 | 陸の豊かさも守ろう |
| 目標16 | 平和と公正をすべての人に |
| 目標17 | パートナーシップで目標を達成しよう |
外務省|JAPAN SDGs Action Platformをもとに作成
17の目標は、以下のように「5つのP」に分けられます。
- People(人間)
- Prosperity(繁栄)
- Planet(地球)
- Peace(平和)
- Partnership(パートナーシップ)
目標の1〜6までは主に人権に関することで、「People」に分類されます。
貧困と飢餓を終わらせ、すべての人に健康的な生活や質の高い教育、水と衛生を確保することが目標です。
また、ジェンダー平等を達成して女性と女児に対する差別をなくし、リーダーシップがとれる社会にすることを定めています。
目標の7〜11までは主に豊かな暮らしの実現に関することで、「Prosperity」に分類されます。
エネルギーへのアクセスの確保や産業化の促進などを図り、持続可能な都市を実現することが目標です。
また、雇用の促進と不平等の是正を定めています。
目標の12〜15までは主に地球環境に関することで、「Planet」に分類されます。
持続可能な消費生産形態の確保や気候変動を軽減するための対策が目標です。
また、海洋資源の保全や、森林などの陸上資源を持続可能な形で経営することを定めています。
目標の16が「Peace」に分類されます。
子供に対する暴力をなくし、すべての人々が司法を利用できるようにすることが目標です。
目標の17が「Partnership」に分類されます。
開発途上国に国際的な支援をおこない、資金を集めることが目標です。
開発途上国の持続可能な開発のため知識や技術の面でも協力し、補うことを定めています。
SDGsに関する日本の現状と課題

世界で進められているSDGsですが、日本で具体的におこなわれていることや、今後の課題などが把握できていない方も多いかと思います。
本章では、SDGsに関する日本の現状と課題について解説します。
SDGsに関する日本の現状
日本ではSDGs推進本部が中心となり、2016年に「SDGs実施指針」を定め、以下の8つの優先課題を提示しました。
| People(人間) |
(1)あらゆる人々の活躍の推進 (2)健康・長寿の達成 |
|---|---|
| Prosperity(繁栄) |
(3)成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション (4)持続可能で強靱な国土と質の高いインフラの整備 |
| Planet(地球) |
(5)省・再生可能エネルギー、気候変動対策、循環型社会 (6)生物多様性、森林、海洋等の環境の保全 |
| Peace(平和) | (7)平和と安全・安心社会の実現 |
| Partnership(パートナーシップ) | (8)SDGs実施推進の体制と手段 |
環境省|持続可能な開発目標(SDGs)実施指針を引用し作成
以上の優先課題を解決に導くため、日本では毎年「SDGsアクションプラン」が公表されています。
また、2017年には、SDGsに関する優れた取り組みを実施した企業や団体を表彰する「ジャパンSDGsアワード」が創設されました。
これまでにさまざまな企業や団体が表彰されています。
SDGsに関する日本の課題
世界中のSDGsに対する進捗状況をまとめたレポートである「持続可能な開発報告書」が、毎年6月に公表されています。
2023年の日本の順位は21位と、はじめてレポートが公表された2016年からの順位低下が顕著です。
順位が低下している理由として、日本ではジェンダー平等の実現や気候変動への対策、つくる責任つかう責任の目標達成度が低いといわれています。
日本では女性議員の少なさや、女性の非正規雇用の多さが目立っていることからも、ジェンダー平等の実現には届いていない状況であることは明らかです。
また、つくる責任つかう責任の面でも以下のような課題があります。
- 原油などを輸入に頼っており、エネルギー自給率が低い
- フードロスが多い
日本は原油がほぼ採れない環境にあるため、ガソリンや軽油などを作るために必要な原油を輸入に頼っています。
また、日本で起きている大量のフードロスも問題です。
フードロスについて、農林水産省の調査によると以下のように述べられています。
令和3年度の食品ロス量は523万トン(前年度比+1万トン)、このうち食品関連事業者から発生する事業系食品ロス量は279万トン(前年度比+4万トン)、家庭から発生する家庭系食品ロス量は244万トン(前年度比▲3万トン)となりました
家庭で発生しているフードロスも含め、毎年大量のフードロスが発生していることがわかります。
また、農林水産省の「食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告における 食品廃棄物等の発生量及び再生利用の実施量(令和2年度実績:都道府県別)」によると、令和2年度の佐賀県の食品廃棄物等の年間発生量は、93,659トンでした。
出典:農林水産省|食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告における 食品廃棄物等の発生量及び再生利用の実施量(令和2年度実績:都道府県別)
佐賀県では食品ロスを削減するため、食育の推進や情報の発信など現在もさまざまな取り組みが実施されています。
SDGsの目標を達成するためには、以上のジェンダー平等や気候変動対策、つくる責任つかう責任の課題を解決しなければいけません。
日常生活でできるSDGsの簡単な例

SDGsの取り組みは、以下のように日常生活でもできます。
- ペットボトルや紙パック、アルミ缶のリサイクル
- 電気や水の節約
- フードロスの削減
- フェアトレード商品に着目
- 普段から寄付を意識
- マイボトルやマイ箸などの持参
- 公共交通機関の利用
本章では、日常生活でできるSDGsの簡単な例を紹介します。
ペットボトルや紙パック、アルミ缶のリサイクル
日常生活でできるSDGsの簡単な例1つめは、「ペットボトルや紙パック、アルミ缶のリサイクル」です。
リサイクルはSDGsの目標12や13、15の達成につながります。
ペットボトルの原料であるプラスチックは石油から作られ、紙パックは木材から作られています。
そのためリサイクルをしなければ、今後も石油や木材などの貴重な資源が失われていく可能性が高いです。
ペットボトルや紙などをリサイクルすることで、地球上の有限な資源の枯渇を抑えられます。
また、アルミニウムはボーキサイトから電気分解して作られていますが、製造過程では大量の電気を消費します。
アルミ缶をリサイクルするとエネルギーの消費を抑えられるため、資源や環境の保護が可能です。
電気や水の節約
日常生活でできるSDGsの簡単な例2つめは、「電気や水の節約」です。
電気や水は作られる過程で大量のエネルギーが消費され、温室効果ガスも排出されます。
そのため以下のように節電、節水を意識しましょう。
- テレビや照明が必要ないときは消す
- 冷蔵庫の開閉回数を減らす
- お風呂に入るときはシャワーをこまめに止める
- バスタブにペットボトルを入れてかさ増しする
日常生活でできる節電、節水方法を積極的におこなうことで、温室効果ガスを削減でき環境の保護が可能です。
SDGsの目標13の達成にもつながるため、無駄遣いを減らすことが大切です。
フードロスの削減
日常生活でできるSDGsの簡単な例3つめは、「フードロスの削減」です。
日本ではフードロスが多く、現在も深刻な状況が続いています。
フードロスを削減するため、以下を意識してください。
- 食べきれない量の食材を購入しない
- 外食した際に注文しすぎない
- スーパーなどに買い物に行く前に冷蔵庫の食材をチェックする
- 購入後にすぐ消費する場合は、手前に並んでいる食材から購入する
他にも、型崩れや傷などがあるため、通常よりも安い価格で売られている「訳あり商品」を購入することも、フードロスを防ぐことにつながります。
フードロスはSDGsの目標2や12に関係しているため、フードロスを削減することで目標達成に近づきます。
フェアトレード商品に着目
日常生活でできるSDGsの簡単な例4つめは、「フェアトレード商品に着目」です。
フェアトレード商品とは、開発途上国で作られ、公正な取引のもと販売されている商品のことをいいます。
フェアトレード商品を購入することは、開発途上国の生産者の労働環境を改善することにもつながるため、SDGsの目標1や8の達成を目指せます。
普段から寄付を意識
日常生活でできるSDGsの簡単な例5つめは、「普段から寄付を意識」です。
寄付先によっても異なりますが、寄付はSDGsの目標2や3などにつながります。
本や衣類など物品の寄付ができる団体もあるため、すぐに捨てることなく普段から寄付できないか考えることが大切です。
マイボトルやマイ箸などの持参
日常生活でできるSDGsの簡単な例6つめは、「マイボトルやマイ箸などの持参」です。
マイボトルを持つことでペットボトルの利用を減らし、マイ箸を持つことで割り箸の利用を減らすと、SDGsの目標12の達成に近づきます。
マイボトルやマイ箸を持ち歩くことは、原油や木材など地球上にある大切な資源の消費を抑え、環境を保護することにつながります。
公共交通機関の利用
日常生活でできるSDGsの簡単な例7つめは、「公共交通機関の利用」です。
自動車は、排気ガスが環境に悪影響を与えることに加え、電車やバスのように一度に多くの人を乗せられません。
そのため、公共交通機関を利用することで、温室効果ガスの排出を減らす必要があります。
また、自動車を使わなくても行ける距離であれば、徒歩や自転車で移動するように心がけると良いです。
SDGsの目標11や13にも関係しているため、日常生活でも自動車を使わない移動を意識してください。
日常生活でできるSDGsの取り組みのまとめ
今回は、日常生活でできるSDGsの取り組みをご紹介しました。
日常生活でできる取り組みは、以下のように多くあります。
- ペットボトルや紙パック、アルミ缶のリサイクル
- 電気や水の節約
- フードロスの削減
- フェアトレード商品に着目
- 普段から寄付を意識
- マイボトルやマイ箸などの持参
- 公共交通機関の利用
小さなことでも取り組むとSDGsの目標達成に近づき、現在地球上で起きている問題の解決につながります。
持続可能な世界を実現するためにできることはないか、普段から考えるように心がけてみるのはいかがでしょうか。