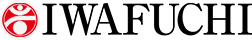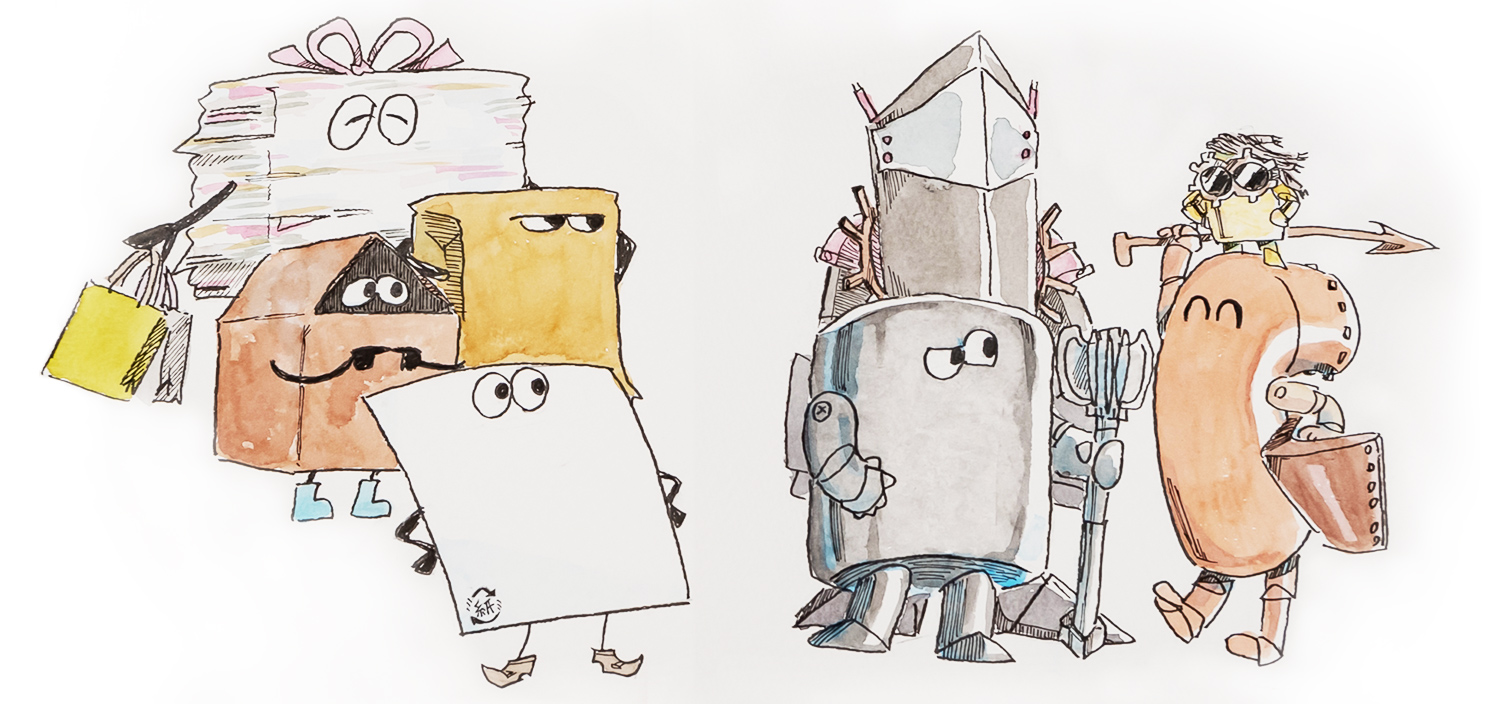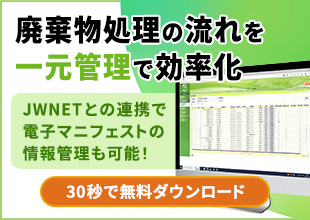今、私たちが日々手にするプラスチック製品の多くは、一度使われるとごみとして捨てられてしまいます。
しかし、この状況を変える取り組みとして、国や自治体はプラスチック再商品化を進めています。
廃棄されたプラスチックを、可能な限りごみにせず、資源として使う。
再商品化は、プラスチックの無駄遣いを減らし、捨てられていたプラスチックに新たな価値を生み出す技術として期待されています。
この記事では、プラスチックごみの問題点から、再商品化の仕組みや、私たちの生活にどのようなメリットをもたらすのかを分かりやすく解説します。
目次
プラスチック再商品化は容器包装リサイクル法の一部
プラスチックの再商品化とは、ごみとして出されたプラスチックごみをリサイクルし、新たなプラスチック商品にしたり、原料にしたりすることを指します。
再商品化は、容器包装リサイクル法(ごみとして出されるお弁当の容器や梱包材などのリサイクルに)で定められています。
容器包装リサイクル法の対象品は、家庭から出るごみを減らし、資源の有効活用ができるプラスチックやガラスビン、紙など、資源として出しているごみです。
プラスチックごみにおける再商品化の概要は、以下のとおりです。
【対象品(プラスチック)】
| 対象品 | 例 | 再商品化後の製品 |
|---|---|---|
| ペットボトル | 飲料、しょうゆ、お酒、調味料ボトル など | ペレット(プラスチック製品をつくる原材料) |
| プラスチック容器・包装 | 食品トレイ、レジ袋 |
【再商品化されるまで】

一般消費者が分別してごみに出す → 市区町村がさらに分別収集 → 再商品化事業者が再商品化
(洗浄・破砕 → ペレット化)
参考:
A-1.容器包装リサイクル法の概要|環境省
再商品化の義務|公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
製品プラスチックは再商品化できなかった?

プラスチック再商品化は、これまで容器包装に限定されており、製品プラスチックは、燃えるごみとして処理されていました。
製品プラスチックとは、プラスチックのみでつくられている製品(商品)のことで、おもちゃや文房具、ハンガーなどが挙げられます。
皆さんも家庭ごみを出すときにおもちゃや文房具が入っている袋は、プラスチックごみ。
おもちゃ、文房具、ハンガーを燃えるごみとして出すことに違和感を覚えた経験はありませんか?
同じプラスチック素材でも、再商品化できるものとできないものがある。
これは、私たちにとってプラスチックごみの分別をわかりにくくしている要因かつ、プラスチックリサイクルの妨げにもなっています。
参考:
【2024年度版】廃プラスチック回収・リサイクルの現状|リバー株式会社
平成29年度プラスチック製容器包装再生処理ガイドライン|公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
対象外だったプラスチックも再商品化できるように!
そこで環境省は、プラスチック資源循環促進法(以下、プラ新法)の改訂に踏み切りました。
具体的には、
- 対象品の拡大(製品プラスチックなど)
- 一般消消費者にわかりやすい分別ルール
- 市区町村における再商品化の仕組み化
です。
これにより、プラスチックごみ全体の再商品化を実現し、以前に増してリサイクルを進められるようになりました。
プラ新法によるプラスチックの再商品化では、家庭から収集したプラスチックごみを市区町村が2つの方法で再商品化します。
市区町村からリサイクル協会に委託する方法
市区町村からリサイクル協会に委託する方法は、これまでの方法と変わらずリサイクル協会主導のもと再商品化されます。
市区町村が選別・圧縮梱包
↓
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会(以下、リサイクル協会)に委託
↓
リサイクル協会が異物除去、洗浄、破砕
↓
プラスチック原料に再商品化される
市区町村自ら再商品化をする方法
プラ新法により追加された市区町村が自ら再商品化をする方法は、効率的なごみの収集が可能になりました。
市区町村が再商品化の計画を作成
必要に応じて再商品化事業者と連携をする
↓
再商品化事業者として国の認定を受ける
↓
認定取得
↓
市区町村と再商品化事業者の連携により
異物除去、洗浄、破砕
↓
プラスチック原料に再商品化
市町村が国の認定を受け再商品化する場合は、リサイクル協会に委託する際に必要な選別や梱包などの工程を省略できます。
そのため、容器包装とプラスチック製品の一括回収が可能になり、効率的なごみ収集が可能になったのです。
市区町村以外がおこなう再商品化
プラ新法のおかげで、家庭ごみ以外もプラスチックの再商品化が促進されました。
プラスチック製品の製造・販売事業者の再商品化
プラスチック製品をつくっている製造業者や販売事業者は、消費者が使い終わった製品を自主回収し、リサイクル。プラスチック原料として再商品化しています。
自主回収は、スーパーや雑貨店、おもちゃ屋などに回収BOXを設置する方法でおこなっています
排出事業者による再資源化
企業から出るごみ(産業廃棄物)は、排出する企業が自らもしくは処理業者に委託します。
委託された処理業者は、プラスチック製品や原料に再商品化したり、処理施設を稼働するエネルギーにしたりと、プラスチックを資源として活用しています。
環境に優しい製品設計
環境に優しい製品設計とは、捨てるときのことを考えて分別や再利用しやすい工夫がされた仕様です。
異なる種類のプラスチックを組み合わせるのではなく、同じ種類のプラスチックを使用する、分解しやすい設計にする工夫をしています。
また、再商品化された原料を使用して、環境負荷の少ない製品づくりが意識されています。
使い捨てプラスチックの削減
プラ新法は、プラスチックの無駄遣いを減らすことに焦点を当てています。
スプーンやストローなど、使い捨てプラスチック製品の使用を減らすリデュースも再商品化の促進に一役買っています。
参考:
プラスチック資源循環促進法の施行について|公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
1.市町村による分別収集|公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
全国第1号!製品プラスチック一括回収・リサイクルに係る大臣認定を取得しました|仙台市
2022年4月スタート ~10分で分かる「プラスチック資源循環促進法」~|リバー株式会社
4.プラスチックの再商品化と私たちの生活の関係性は?
プラスチックの再商品化は、ごみを減らす環境に良い活動ですが、私たちの生活にどのような関係があるのでしょうか。
環境への貢献を実感できる
プラスチックごみとして捨てられる対象品が増えたため、多くの市町村や企業はプラスチックの回収拠点を増やそうとしています。
回収ボックスやゴミ処理場への持ち込みなど、家庭ごみとして出す以外の選択肢も広がり、分別・回収に協力しやすくなりました。
たとえば、株式会社マクドナルドでは、燃えるゴミとして捨てられていたハッピーセットのおもちゃ回収ボックスを設置しました。
回収されたおもちゃは、粉砕処理を経て樹脂原料となり、新たなトレイとして再商品化されています。
自治体や企業がおこなうプラスチック再商品化の取り組みに賛同することで、環境保護に貢献していると感じられます。
参考:
ハッピーセット®︎のおもちゃリサイクル|株式会社マクドナルド
環境に優しいプラスチック製品を選べる
市区町村以外がおこなう再商品化の動きとして、環境に配慮された製品や、リサイクル素材を使用した製品が増えました。
環境に配慮された製品とは、リサイクルしやすい素材や製造工程でつくられた商品です。
これらの製品が増え、購入するものの選択肢が広がると、製造する企業は、さらに環境に配慮した製品をつくり安く販売できます。
私たちは、環境に配慮しながらも好きなデザイン、好きな企業の製品が購入できるようになるでしょう。
これまで、サスティナブル商品や環境に配慮された製品は、割高なイメージがありました。
再商品化のおかげで、環境に優しいプラスチック製品を気軽に選べ、環境を考えた生活のハードルが下げられそうです。
【重要】リデュースとリユースの取り組みを忘れてはいけない
再商品化は、いわゆるリサイクルです。
プラ新法は無駄遣い削減のため、再商品化を促進していますが、再商品化だけでは無駄遣いを減らせません。
まずは「捨てるものを減らす」ことがなによりも重要です。
ぜひ、次の順番を意識してプラスチックを購入し、捨てる判断をしていきましょう。
順番1:購入するときに長く使えるか考える(リデュース)
順番2:捨てる前に再利用できないか考える(リユース)
順番3:市区町村の分別ルールに従って分別して捨てる
どんなに「捨てるものを減らす」が大事でも、捨てる行為に罪悪感を抱く必要はありません。
分別ルールをしっかり守れば、再商品化されることを意識して捨てれば問題ないからです。
順番を意識するだけでプラスチックの無駄遣いを減らせますので、ぜひ上記を参考にしてみてください。
江北町が九州初のその他プラスチック原料を含めた再商品化事業の認定を受けました
佐賀県杵島郡江北町は、九州初となるプラスチック容器包装およびその他プラスチック原料の再商品化計画の認定を受けました。
2025年4月より、全国で14番目のプラスチック資源一括回収ができる自治体として、プラスチックの再商品化に取り組みます。
これにより、江北町にお住まいの方は、「容器包装プラスチック」と「その他プラスチック原料」を一緒にプラスチックごみとして捨てられるようになります。
株式会社イワフチは、前述のプラスチック再商品化計画において、再商品化前の中間処理(圧縮)を担うことになりました。
弊社で圧縮したプラスチックは、再商品化事業者である株式会社エコポート九州のもとでペレット化(再商品化)され、新たな製品に生まれ変わります。
参考:
プラスチック資源循環促進法第33条に基づく再商品化計画の認定について (容器包装プラスチック+製品プラスチックの認定は“九州初”)|環境省
九州初!家庭から集めたプラスチック資源(製品プラスチック)のリサイクル計画が国から認定されました|北九州市
佐賀県江北町の再商品化計画認定授与式に出席しました|株式会社エコポート九州
まとめ
プラスチックの再商品化とは、
- プラスチックごみをリサイクルし、新たなプラスチック商品または原料にすること
- これまでは、容器包装に限定されていたため一部のプラスチックごみは燃えるごみだった
- プラ新法により、すべてのプラスチックごみが再商品化できるようになった
- 認定を受けた市区町村は、プラスチックごみの一括回収および再商品化ができる
- リデュース、リユース、リサイクルの意識で、プラスチックの無駄使いを減らすことが大事
です。
プラ新法により、すべてのプラスチックごみを再商品化できる仕組みがつくられましたが、再商品化の進み具合は、地域によって差があります。
お住まいの地域で、再商品化の取り組みが進んでいなくても、”分別の徹底”により再商品化やプラスチックごみの削減に十分な貢献が可能です。
株式会社イワフチでは、再商品化を含むリサイクルやごみの正しい知識を広めようと、みなさまにコラムをお届けしています。
今後も、プラスチックをはじめとするごみのリサイクルをより一層推進していきます。
弊社のお役立ちコラムをご活用いただき、正しい知識で今よりリサイクルができる環境をつくっていきましょう。